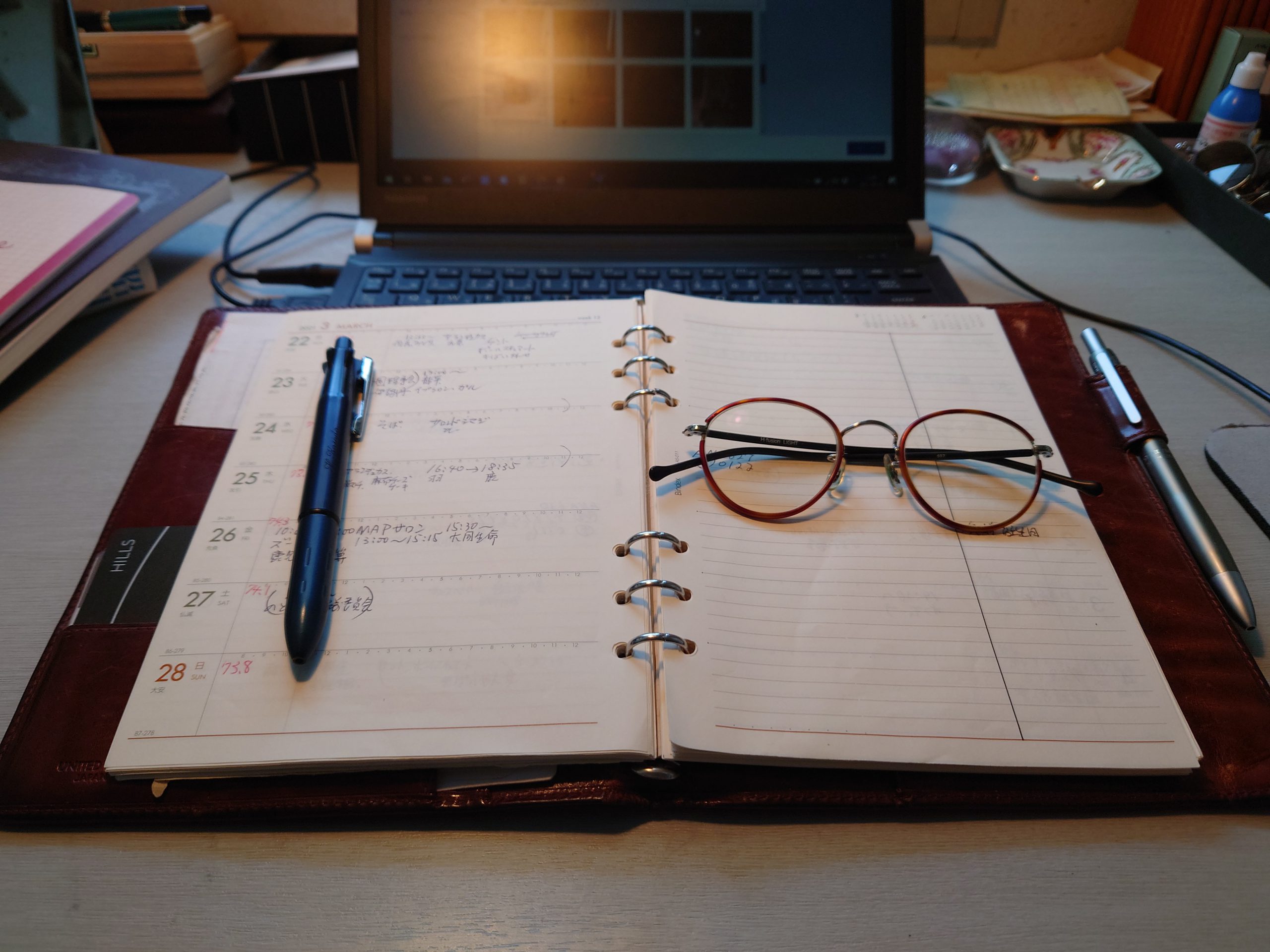人口が増えているときには通用する「安易な稼ぎ方」―観光産業をモデルに日本の生産性の低さを考える―Ⅲ
人口増加時代、「量」を追及していた日本の観光産業の経営戦略(「経営戦略」といえるほどのものだったかどうかは疑問ですが・・・)は、やがて破綻をきたします。
そのプロセスをアトキンソン氏は次のように指摘されています。
―人口が増えていた時代の旅行のほとんどは国内旅行でした。
そのため、滞在日数も短く、ゴールデンウィークや夏休みなどの特定の期間にお客さんが集中する一方、それ以外の季節はあまり人が集まらず、閑散期の長い非効率な業界でもありました。
一方、繁忙期には黙っていてもお客さんが集まります。
この2つの要因によって、当時は個々の観光資源に付加価値をつけるというインセンティブが働かず、観光地としての整備レベルが相対的に低いまま放置されていました。
当然、お客さんの満足度も決して高くはなかったはずですが、それすら「当たり前のこと」として見逃されていました。
要するに、単価が低くても、数の原理で売り上げを増やせばいいというビジネスモデルだったと言えます。
厳しい言い方をすれば「安易な稼ぎ方」でした。
単価が低いから満足度も低くていいというのは、人口が増えているときには通用するロジックだったかもしれませんが、人口が減り始めた今、そんなことは言っていられません。―
いやはや、何とも厳しいご指摘です。
少し視点ずらした感想になりますが、私なりに日本の観光業に感じたことがありました。
それは私が自分の家を建ててからのことになります。
私と家内は、家を建てるときそれなりにこだわりました。
中でも内装に関しては洗面所やお風呂などの水回り、トイレの機能と形状、床材やドアなどの色や素材・・・あれこれと吟味したものです。
その自分の家を持ったあと、税理士会などの慰安旅行で出かけた先で、観光地のホテルの設備が何ともプアなことに気づいたのです。
私もそれほど豪華な素材や機材を使用したわけではありませんが、それよりもはるかに劣っているホテルの設備調度品を見るにつけ、「客からお金をいただいていてこれかよ!」と半ばあきれたものです。
つづく