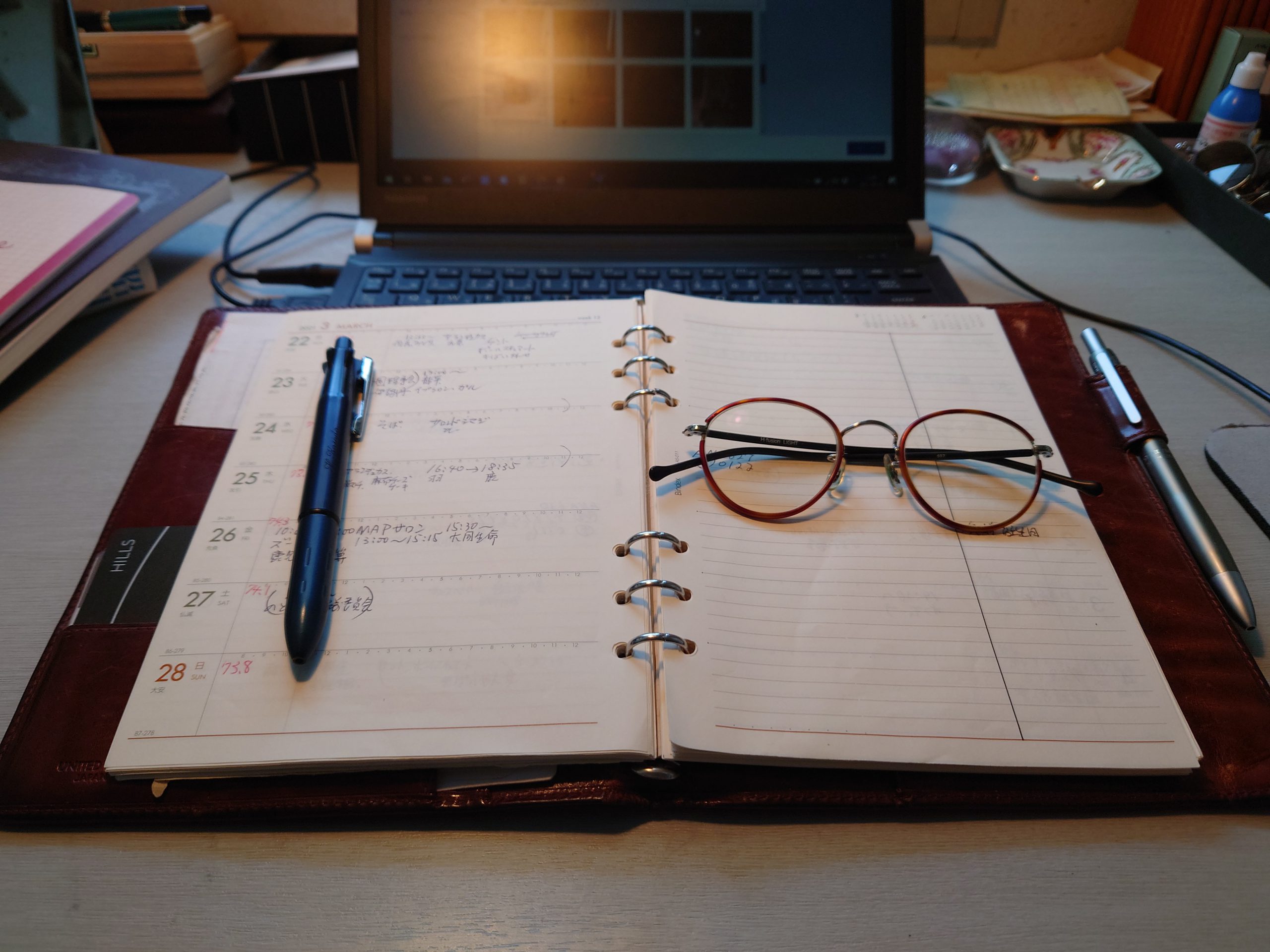広告宣伝はどう届くのか?―広告宣伝の持つ性格について改めて考える―Ⅰ
前回までのブログで経費としての「広告宣伝費」について触れました。
その中で、業績が下がったからといって、安易に「広告宣伝費」を削るべきではないということとその理由についてお伝えしたつもりです。
とはいえ、「広告宣伝費」の負担が中小企業にとって大きいことに変わりはありません。
経営者としては、何とか工夫してこの負担を軽減する方法を考える必要がありそうです。
ただ、「広告宣伝費」に関するコスト負担が重くて苦しいというのは、いわばこっち側の事情です。
それが商品価格に大きくはね返らない限り、消費者には直接関係のない問題と言っていいでしょう。
つまり、「広告宣伝費」に予算をかけなかった結果、売上が上がらなかったからと言って誰のせいにもできないということです。
そのことだけは意識しておいて下さい。
「広告宣伝費」負担の問題については、後ほどまた触れることにします。
ところで、広告宣伝にはもう一つ大きな課題があります。
それは「消費者にどう届くか」、という課題です。
広告というのは、最終的に「売らんかな」が目的のために、自社の商品についてポジティブな情報のみ伝えて、ネガティブな情報を流すことは通常あり得ない、と一般的な消費者は捉えています。
つまり、広告はその作り込みやイメージがどんなに巧みで優れていても、消費者にとっては、どこかに「売り込まれている」という意識が付いて回ることになるのです。
それを払拭するために「パブリシティー」という手法があるのはご存知の通りです。
これは、自社や自社の商材について、第3者(主にメディア)に記事として取り上げてもらうので、広告者側の恣意性が入らず公正であるという訳です。
また、原則お金もかかりません。
つづく