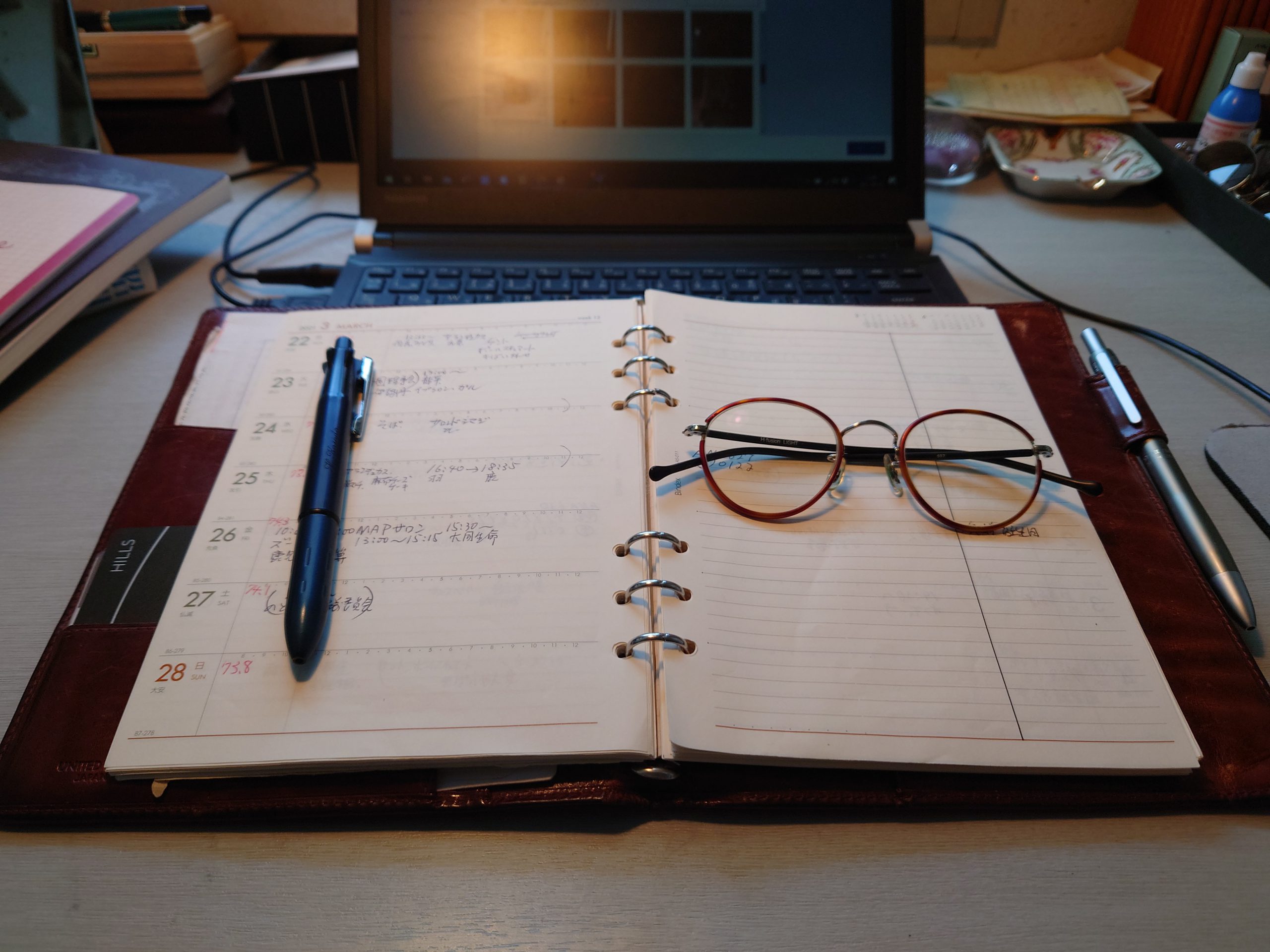移ろいゆく「家族」という形―それぞれの世代がそれぞれの家庭という城を築いている―
一緒にランチにしようよ
先日、カミさんを交えて二人の娘たちと私、4人で昼飯を食っているときふと考えた。家族、家庭というものの存在とその移ろいゆく姿について。
数日前のことだった。昼前、長女から「ランチ一緒にしようよ。」と連絡が入ったのは。上京してきてもう5日目。考えてみれば、近くに住む娘たちとはまだ会っていなかった。
私には二人の娘がいる。(さらにその下に長男もいる。)長女と次女、娘たち二人はそれぞれ家庭を持って東京で暮らしている。お互いの家は近いのだが、どういうわけかカミさんもその近くに住んでいる。千葉に住む長男と鹿児島で暮らす私、我が家ではこの男二人だけが田舎暮らしなのだ。
この辺の事情は何回かこのブログでも書いてきた。普段田舎で暮らす私は、ときどき上京して家族との時間を過ごす。
もちろん支払いはこちら持ち
先日のランチもそんな日々の一コマだった。
「ランチしようよ。」のお誘いは、向こうから声がかかることが多い。こちらから声をかけないのは、小さな子育て中で忙しいあの子たちの邪魔をしてはいけない、との配慮からである。
そうやって向こうから声のかかったランチでも、もちろん支払いはこちら持ちである。まあ、普段大して親らしいこともしていないから、その埋め合わせというわけでもう慣れっこである。
尤もカミさんは、小さな孫たちの面倒を見ることを含めて、娘たち家族にはいろいろと貢献しているから、埋め合わせなんて考える必要もない。不良じいじである私のせめてもの償いといっていいだろう。
カミさんは、ただ便乗して一緒の時間をこうやって過ごしているのだ。まあ、日常の中で、たまに巡ってくる楽しいひとときである。
そう、当たり前のことなのだ
そんなランチタイムでの話題はもっぱら娘の子供たち、私とカミさんから見れば孫たちのことである。小学校入学前の検討課題や将来の進路などに関して、長女と次女それにカミさんを交えて熱心に話している。
そういった話題に関しては、私はひたすら聞き役である。孫たちの進路やなんかに、私があれこれ口を出すことなどしない。
こんな話題に夢中になっている娘たちを見ていてふと思った。
『ああ、この子たちもすっかり自分の家庭を持ったんだなあ。』
と。
「なんだ!当たり前のことじゃないか。」と思われることだろう。そう。当たり前のことなのである。ただ、冒頭述べたように、ふとそのことを少し突っ込んで考えてみたのだ。
やがて終わりの形を迎える
そのランチタイムの数日前、妹と晩飯を食った。妹も東京暮らしである。上京した際には、こうして独身の妹と飯を食う。
ところで考えてみれば、妹だけでなく、もう一人の兄弟である弟を含めて、私以外はみんな東京暮らしではないか。長男がちょっと離れていると言っても、すぐ隣りの千葉である。本当の田舎暮らしは俺だけか、なんてことが頭をよぎったが、まあそれはどうでもいい。
妹とは、現在鹿児島の田舎で老人ホームに入っている母の話題になった。父は数年前に亡くなっている。母は長生きして今94歳である。
私と弟、それに妹の3人は、その父と母のもとで育った。母も上述のように高齢だから、早晩、我々兄弟だけが残されることになるだろう。こうして、父と母それに私たち3人兄弟の5人だった私の家族は、やがて終わりの形を迎えることになる。
5人家族で暮らした時間は短かった
振り返ってみれば、この5人家族で暮らした時間は割と短い方だったかも知れない。私も弟も中学から進学を理由に家を出たからである。
そうして教育のために大きな負担をしてくれた両親には感謝しているが、5人そろった家族としての生活はそう長くはなかったことになる。このことは妹にとって、あまりいい結果にはならなかったようだ。
両親二人と一人残された妹の3人の生活は、どちらかと言えばかなり窮屈で息苦しいものだったらしい。両親の仲があまりいい方とは言えず、暖かで穏やかな家庭生活とはいかなかったのだ。まあその話も今回はどうでもいい。
その私たち兄弟と親たちとの家庭生活、家族関係というのは、先述のように間もなく終わりを迎えようとしている。途中、それと重複して別の家庭、家族も生まれた。
強い粘着力ののりしろ部分が続いた
私の場合は、結婚してすぐに長女が生まれ、自分の家庭、家族を持つことになった。当時は私の両親ともまだ元気であり、仕事も現役だったので、自分の家族と親との関係の両方に気を配る必要があった。
新しい家庭、家族が生まれたとしても、それまで自分が所属してきた上の世代の家族との関係がなくなるわけではない。その両方が重なっている期間は、かなり粘着力の強いのりしろ部分が続くことになる。
つまり、親世代との人間関係である。これが、ともすれば難しい状況に陥りやすいのだ。
まあ、どんな人間にも大人になれば起こり得る普通の状況と言えよう。しかし、この現実が意外に大変なのである。と、いう事実にその当事者になって初めて気づかされた。
原則はこうであろう。即ち、新しい家庭家族ができたならば、その当事者である夫婦は、そっちに軸足を置いて生活を送っていくことになる。そうするのが当り前で自然というものだ。
前の世代に対して気を配れという風潮
ところが、現実にはなかなかそうはいかない。前述のように前の家族の引力が意外に強いからである。
まずは自分たちで持つことになった家庭家族に、全力を尽くして向き合うべきなのに、前の家族(親や兄弟)とのしがらみが思った以上に大きいのである。例えば、世の中でよく問題になる「嫁姑の確執」などその典型であろう。
しかし今回はその確執に焦点を当てる気はない。私にもいろいろあったのだがそれはまた別の機会に書こうと思う。
冒頭、ふと考えたというのは、世代が移りそれぞれの家族がこうやって形成されていくんだなあ、という当たり前の現実を、今さらのように感慨深く見つめ直した、ということになるのだろうか。
昔は、前述のようにもっと前の世代に対して気を配れ、注意を払えと言われていた。何につけてもひと世代前、つまり親の世代をもっと立てろ、というのが世の中的風潮としては強かったような気がする。
こうして次の世代が中心になっていくんだなあ
少なくとも私の場合、そのことについては、かなり親の締め付けがきつかった。カミさんの方の両親がそれほどでもなかったので、なおさら際立っていた。とはいえ、先述したように、そのことの恨み節など書き連ねるつもりはない。
世代が移り、私の子供たちもそれぞれが独立し、自分たちなりの家庭を持ち、家族を形成した。娘たちが自分の子供(私から見れば孫)の行く末の心配をしている姿など見ていると、こうして次の世代が中心になっていくんだなあ、とつくづく思ったのだ。
ただ、自分の子供たちとはいえ、その考え方や価値観などすべてに賛同できる、というわけではない。新しい世代の新しい価値観に関しては、私たち世代から理解しかねるようなことも結構あったりする。
とはいえ、私やカミさんが親世代から受けた価値観の押しつけの真似ごとなどする気は全くない。子供たちがどんな家庭を作り上げていくのか。そしてそれをどんないい形で次の世代に継承していくのか、そんな時代の流れを見守るだけである。

ばあばと孫たちの風景