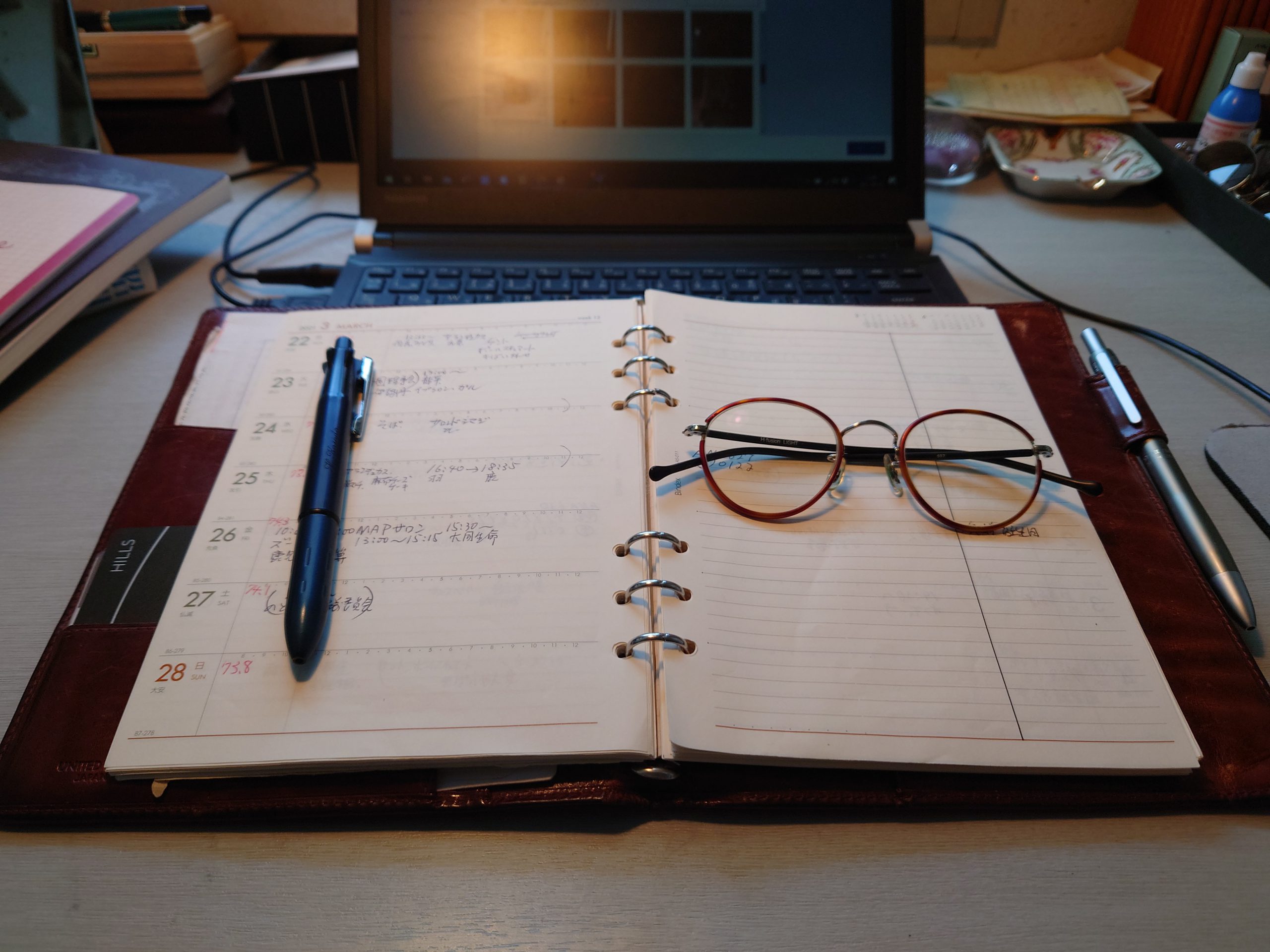「また変えればいいじゃないですか」―コロナ危機、こういうときに抵抗勢力を押し切って一挙に改革を進めよう―Ⅱ
どんなタイプの会議やミーティングでも必ず存在する、その中をかき乱す人たち。
こういった人たちの分析や対処法について、G氏は続けて以下のように書かれています。
―世の中、自分の安全を守りたいがために、さも賢そうにマイナス面を誇大に論じたり、臆病さを隠すために知的ぶって誤魔化そうとしたりする人が、現実にたくさんいる…ということです。(中略)
(ビジネスや経営では)どれだけ怖くても、「決定」していかない限り、ビジネスは確実に終わりに向かってしまうからです。
この手の話をしたときに、「そうは言っても、間違った決定をしたら大変でしょう!」などと、口角泡を飛ばす勢いで言ってくる人がいたりしますが、お返しする言葉は実にシンプルです。
「また変えればいいじゃないですか」です。―
「知的ぶる」或いは「専門家ぶる」というタイプの抵抗勢力には、これまでイヤというほど遭遇してきましたが、その対処法について、G氏は実にシンプルに答えておられます。
目からうろこの感じですね。
そうなんです。
「また変えればいいじゃないか。」
と言えばいいのですね。
そこのところをさらに詳しく見ていきたいと思います。
G氏は続けて次のように書かれています。
―間違った、失敗したと分かったら「変えればいい」だけの話です。
たったこれだけの話です。
一番恐ろしいミスは、「判断しない」「決定しない」「先延ばしにする」…ことです。
判断ミスかどうかも分からず、永遠に取り返せない時間だけが過ぎ去るからです。
もちろん、正しい判断や打ち手というのが良いに決まっています。
しかし、すべて正しい手を打てるかどうかなど、全知全能の神様ではないのですから、100%の正しさで手が打てる人など、絶対にいるはずがないのです。
ところが、世の中にはこの手の思考回路の人が結構多くいます。
「ゼロリスクでないとダメ」、「全員に等しくなければダメ」、「100%確実でなければ」…といった症候群の人たちです。―
ここに書かれていることは極めて重要です。
つまり、トライして試行錯誤を重ねる中で遭遇するミスと、何もしないで取り返しのつかないところまで行ってしまうミスの違いです。
後者の方が大きなミスに決まっているにもかかわらず、前者を選択する人が案外少ないという事実。
これはこういうことではないでしょうか。
つまり前者のトライでミスがあった場合自分の責任になるが、後者の場合は
「世の中の流れがそうだったんだから仕方がなかったんだ。」
と、他者のせいにできるからです。
 こんな感じで「また変えればいいじゃないですか。」と言っているわけではありません。(;´д`)
こんな感じで「また変えればいいじゃないですか。」と言っているわけではありません。(;´д`)
つづく