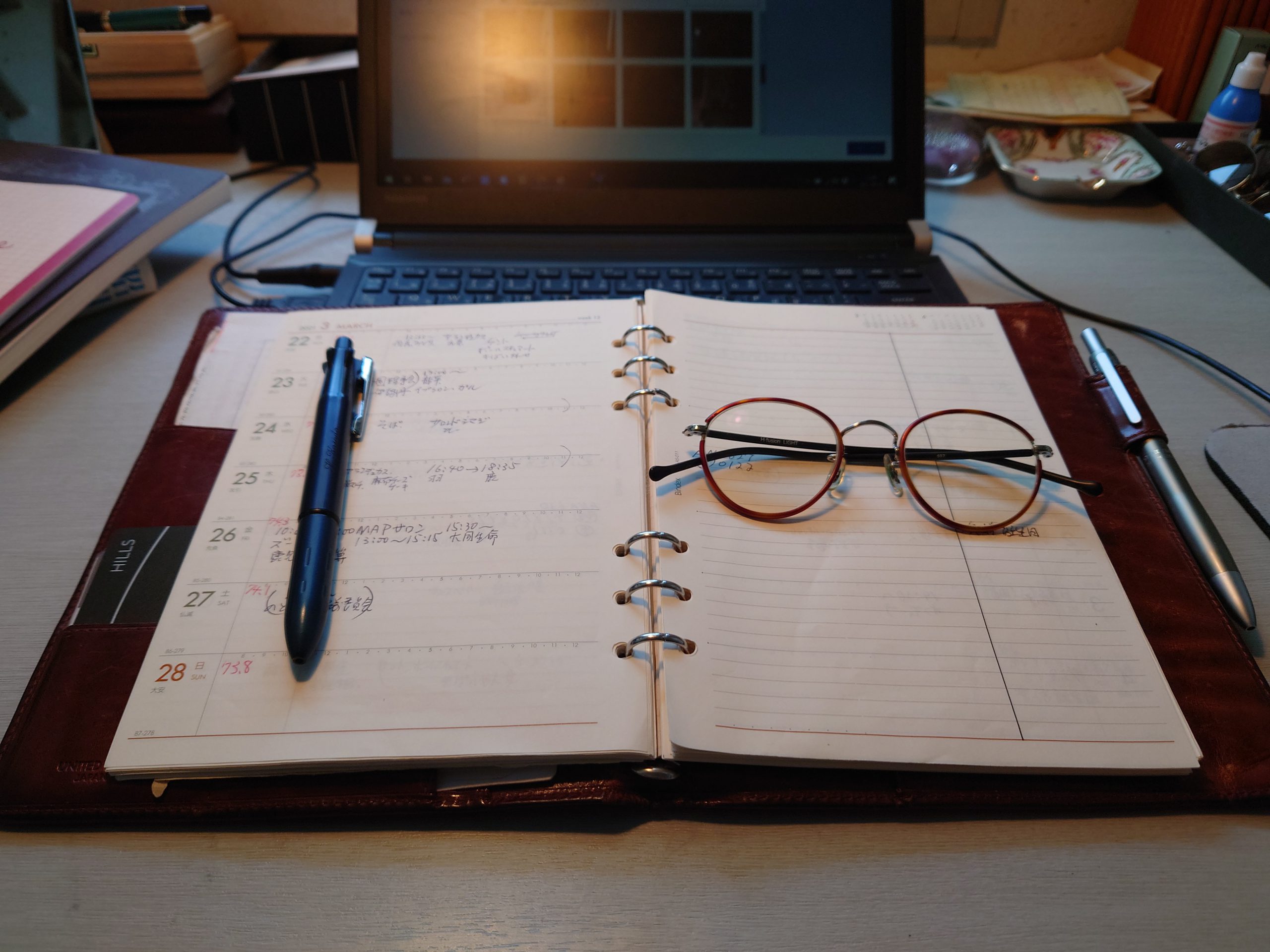俺たちはどこで食っているのか―そのドメイン(事業領域)を考えてみる―
私たちの業界は、基本「税の専門性」を提供する仕事で成立しています。もっと平たく言えば、そこで「食っている」わけです。
ところが、そこのところが、将来性においてどうも「危うい、希望が持てない、消滅するのでは」的なことを言われ続けています。
それはとりもなおさずITテクノロジーの発達、高度化、AIの登場とその凄まじい進化といった時代背景があるからに他なりません。
この点について、現場サイドで考えてみました。我々が提供している業務を客観的に見た時にどうなるか、という視点になります。特に顧客側から見たら税務会計における処理その他の業務がどう映るのか?ということを考えてみました。
我々が提供している専門領域のサービスは、顧客側からは次の3パターンになるのではないでしょうか。
・普通にこっち(顧客側)でできるレベル
・やろうと思えばできるけれど、提供してもらった方が楽な業務
・こちらではできないので依頼せざるを得ない業務
もの凄くざっくりとした分け方ですが、こんな風に考えてみればわかりやすいのでこの3パターンに分けてみました。あくまでも顧客側の立場に立った見解です。
・普通にこっちでできるレベル
ここが昔はままならなかったので、我々にその多くが依頼されていたのでした。いわゆる記帳代行の世界です。一年にいっぺん、領収書をドサッと持ってきて「はいお願いね。」と言われていたレベルです。
しかし、この領域については、自計化(=コンピュータ会計)の導入が進み、期中においても顧客側の記帳負担がかなり省力化されました。近年では自計化がさらに進み自動化の領域が大きくなりつつあります。その結果、取引記録を読み込んだ上で、月次の試算表その他の会計データを顧客サイドで出力することも可能になりました。
ということは、会計事務所側がここで報酬を得ていたとすれば、今後そのビジネス領域では、収益の確保が厳しくならざるを得ないと言えます。
つまり、顧客側の「こっちでできるレベル」が昔に比べて確実に進化しているのです。
とはいえ、今のところ、この「普通にこっちでできるレベル」にも顧客によってスキルにかなりの差があります。ちょっとパソコンの操作やデジタル系の環境に詳しい人であればできるであろう世界も、まだまだという層も一定存在するので、このレベルであっても我々への依頼が継続しているのです。
ただ、会計ソフトなどの扱いやすさやそれに伴うデジタル機器の機能や操作性の進化によって、簿記への知識不足、機器の取り扱いの難しさといった課題はどんどん解消されると予測されます。ですから、やはりこの世界は、依頼されるビジネスとしては、やがて消滅すると覚悟しておいた方がいいと予測しています。
・やろうと思えばできるけれど、提供してもらった方が楽な業務
ここはまず第一に、やればできるけれど任した方が効率がいい、という考え方を指します。
コンピュータを駆使して仕事をするプロフェッショナルの世界には、会計事務所よりはるかに高度に使いこなしている人たちがいます。こういう業界の人々にとって、会計ソフトを取り扱うことなど造作もないことのようにも思えますが、実際はどうでしょうか。
私の勝手な推測ですが、現実にはそういったプロフェッショナルであっても、私たちに会計処理を依頼される方が多いのではないでしょうか。実際、私の事務所でも、その手の業界の方で経理業務を依頼される方は一定数存在します。
それは、会計ソフトの操作等ができないわけではなく、本業があまりに忙しいので、それ以外の世界はアウトソーシングした方が効率がいいと判断されたわけです。これは、「やればできるけれど・・」という世界です。
第二に、自分で処理するにはちょっと難しいけれど、頑張ればできなくもない、という世界もあります。
以前、昔からご縁のあったお客さんに相続が発生したことがありました。ある程度資産をお持ちだった先代が亡くなったのです。当然のように、相続税の申告が必要となりました。
ところが、これまで、所得税や法人税の申告は私の事務所に依頼されていたそのお客さんは、「今度は自分でやってみる。」とおっしゃったのです。相続税の申告はなんかできそうだな、と思われたのでしょう。
「難しいんだけどな。」と思いつつ、そう言われるので手を引きました。ところがそれから2カ月もたたないうちに「どうも無理そうなんでやっぱりお願いします。」と連絡が入ったのです。
そう、相続税の申告は、頑張れば一見素人でもできそうに思えるかも知れませんが、現実的にはそれほど簡単ではありません。複雑な要素が絡み合っているため、途中で匙を投げだしてしまわれたらしいのです。税務署でも税理士のところへ行った方がいい、と言われたようでした。
これなどは、無理してやろうと思えばできなくもないけれど、専門家にやってもらった方がはるかに楽な業務の典型と言えるでしょう。
・こちらではできないので依頼せざるを得ない業務
簡単な個人の所得税申告であれば、パソコンどころかスマホでもできる世の中になってきました。ただ、会社組織としての法人税申告となれば、やはり専門家に依頼した方が無難です。というのは、年商など規模が大きくなってきた場合、特に消費税の申告などでミスってしまうと結構大きなペナルティーを課せられるからです。
消費税は、軽減税率の導入、インボイス制度の発足以来、複雑化を極めています。
公平・中立・簡素というのが税の3原則として広く知られていますが、この中で簡素ということに関しては、全く逆の方向へ行っているとしか思えません。
その処理があまりに複雑なため、我々専門家に依頼するしかない、という側面があることは否めない現実です。当然、そこは我々税務会計専門家の出番であり、それがこちらの収益にも繋がっているわけですが、ここで料金をいただくのは我々としても本意ではありません。(ただ、いただかないことにはコスト割れになってしまいます。)簡素化、というのは、税を専門としている我々も望むところなのです。
それから近年重要になってきたテーマとして、「経営計画の策定」ということがあります。金融機関は、企業への融資に際して必ず「経営計画」を求めてくるようになりました。
融資条件として担保や保証人が必須とされてきた昔とは随分様変わりしたことになります。融資に際して金融機関が最も留意するのは返済能力ですが、そこを見極める重要な手段として経営計画を重視するようになってきたのです。
ところが、経営計画と言われても、普通の経営者にそれを「自分で作成しなさい」と要求するのは難しい話ではないでしょうか。当然、我々がお手伝いすることになります。
ただ、これに関しては100%こちらで作成することはしません。やはり、経営者が自分で作ったものでなければ意味がないからです。
ですから、ここは共同作業になります。社長が頭の中で構想している経営計画に具体的に数字を加えたものを一緒に作成するのです。これなどは「依頼せざるを得ない業務(共同作業にはなりますが)」というレベルの話になるのではないでしょうか。
このように、私たち職業会計人が「どうやって食っているのか」と考えたときに、顧客が料金を払っている領域には3段階のレベルがあることがわかります。
私は、両者が良好な関係を続けていくには、できるだけ第1段階のレベルを脱却して、第2、できれば第3段階の高度なサービスのみを提供していけるようなビジネスに進化していく必要があると思っているのです。
自分たちが、どこで食っているのか、というドメイン(事業領域)を常に意識しておくのは、私の業種に限らず大事なことでしょう。
そしてそれが、同じような状況で未来永劫続くことは決してありません。
どんな仕事においても、変化するんだ、ということを念頭に「今後どうなるか」を常に意識しておくべきです。
私もそんな前提で、今の仕事の未来形を構想しているのです。

経営計画となると難しい。