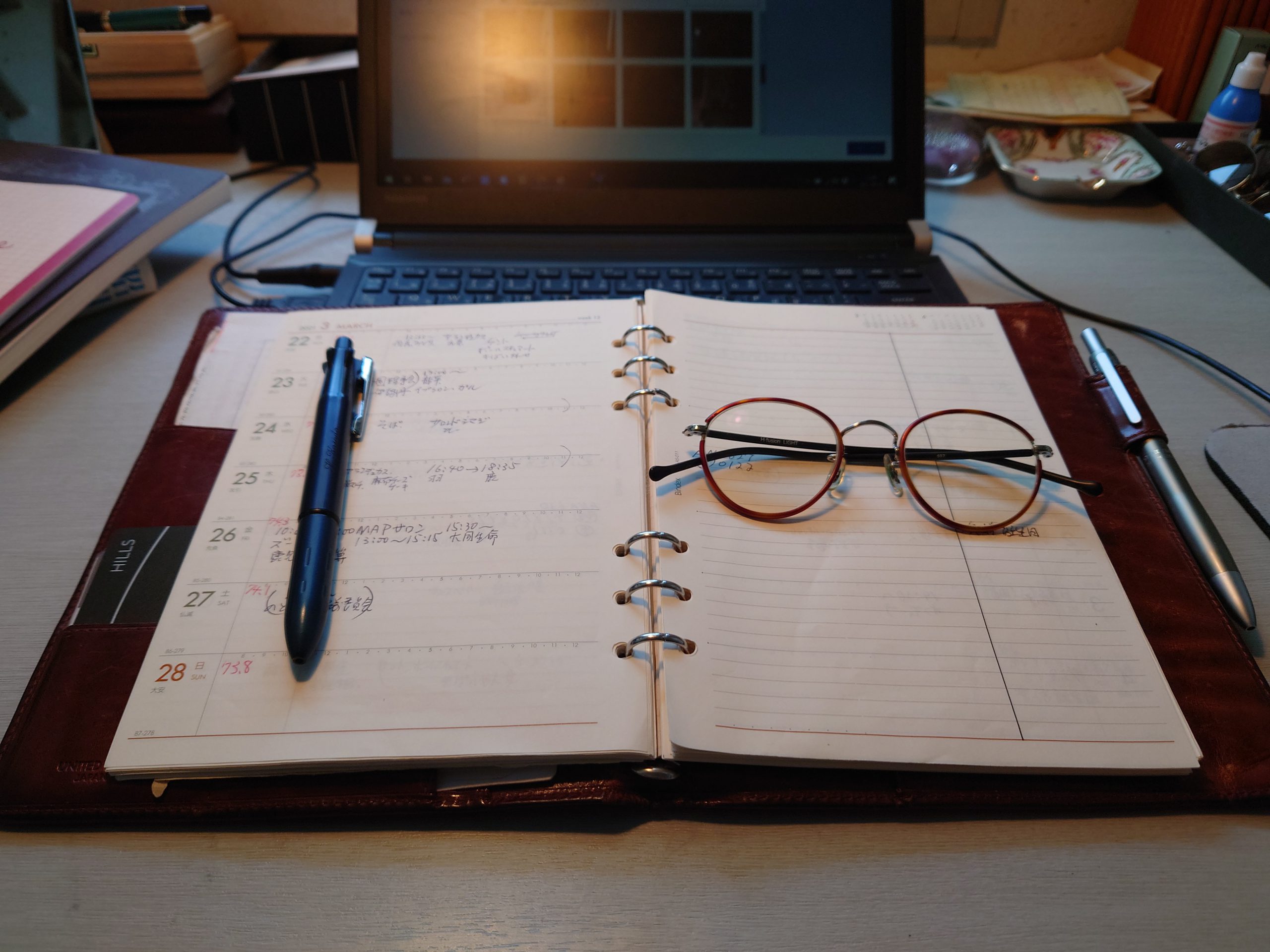地方衰退の原因と再生の処方箋を考えるⅣ
一過性の補助、助成というものがどういう結果をもたらすのか、これまで私も目の当たりにしてそれなりの感想を持っている。
それについてはこの文末で触れたい。
木下氏は以下のように続けておられた。
― 地域の衰退とは何でしょうか。(中略)
「仕事がない」→「仕事がないから人もいなくなる」→「人もいなくなるから、ますます仕事がなくなっていく」、という負の循環をいかにして断ち切るかしかありません。 そのためには、利益を生み出す事業と向き合わなくてはなりません。(中略)
利益が出ないようなことばかり続けていると、地域の経済がいつまでたってもプラスにはなりません。(中略)
足りなくなったらさらに投入せざるをえないという構造になり、活性化とは程遠い状況になります。
地域活性化が「公共性がある→補助金を出す→利益は出していけない」という概念に基づいてしまっていては、限界があります。
行政が関わった途端に、官民両方が利益は出ない、出していけないという固定観念も未だ強いです。(中略)
税金を用いた活性化事業の限界は、利益を出してはいけない、出せないという、その資金の性質と諦めで縛られてしまっているわけです。
逆に言えば、「利益を出せないような活性化事業は、すべて止めてしまう」くらいの、思い切った意思決定が必要なのです。(中略)
「地域で資金を回し続けるエンジンを作り出すこと」、すなわち「しっかり利益を出すこと」でしか、地域の持続的な活性化なんて不可能なわけですから。―
補助金投入の事業というのは、私たち会計人にとって極めて分かりにくい所がある。
これは以前から感じていたことだ。
それは、木下氏がかかれているように「利益を出してはいけない。」という不文律があるということに起因している。
通常、我々は利益を出さないことを前提に事業を行ないはしない。
いかに利益を追求するかに知恵を絞り行動を起こすわけである。
この原則に反した補助金事業というのは、大きな意味で経済の摂理に反しているのである。
これがうまくいかない主たる原因というのは、木下氏の指摘を待つまでもないのだ。
つづく